色鉛筆で描く「 椿 」 清楚な椿の描き方を解説!
こんにちは、たくみです!
今回は
「椿の描き方」になります。
古くは万葉集(奈良時代末期)にも
登場する椿は古来から日本人に
なじみ深い花ですね。
常緑樹でもあり神社やお寺に植えられる
ことの多い日本原産の美しい花です。
そんな清楚でどこか神聖なイメージのある
椿を描いてみましょう!
お花の好きな方やこれから植物画を
始めたい方など参考にしていただけ
ましたら嬉しいです。
― お題 ― 「椿(つばき)」

【 準備するもの 】

【 準備するもの 】
画像にあるケント紙(B5~A4)
参考:ケント紙(A4)
色鉛筆(メーカーは自由です)
参考:プリズマカラー
下書き用の鉛筆、ペン型消しゴム、
そして定着剤(フィキサチーフ)も
あると保存に便利です。
☆ フィキサチーフ 使用方法
※ 作品の汚れ防止としてチラシやコピー
用紙などを手の下に敷いて描きます
それでは
準備のできた方から始めましょう!
1 下書き
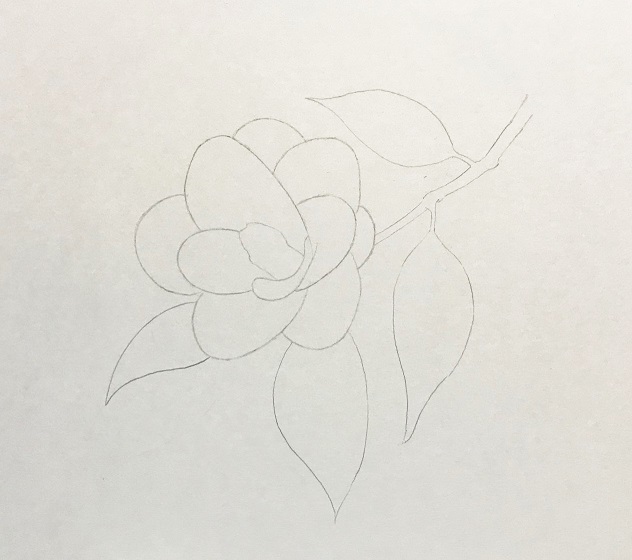
※クリックすると拡大します
画像のように
中央よりやや左下に椿を描き、
右上に枝を伸ばす感じのレイアウトで
下書きしましょう。
2 着色(葯)

雄しべの先端の葯(やく)を
黄色(916)でいくつか着色します。
3 描写(花糸)

鉄筆または細筆の柄で花糸を描写します。
画像のように花糸(おしべ)を数本
ケント紙に強めに跡をつけていきます。

次にピンク色(929)で雄しべの
中央周辺を強めに着色します。
※ 花糸の線は深いので着色されません

このように花弁の中央が着色されました。
4 着色(葯の陰影)

葯の陰影を茶色(943)で描き入れます。
5 着色(花弁‐①)
花弁全体を
ピンク色(929)で着色します。

このように下地が塗られました。
(画像では薄めに見えます)
6 着色(花弁‐②)

同じピンク色(929)で花びらの先端
付近のヒダのようなムラの濃淡を
ところどころ描写していきます。

このような感じでムラのある着色
ができました。
7 着色(花弁‐③)

同じピンク色(929)で花びらの根本から
強めに着色し陰影を表現します。
(左上からの日差しを想定しましょう)

外側もこのように。

下側は花びらの輪郭を先に描いて
そこから着色していきます。

このように陰影が描写されました。
8 着色(葉‐①)

葉の葉脈を黄緑色(912)で描写します。

葉の手前側に深緑色(911)で
葉縁(鋸歯)を描き入れます。
※ギザギザに描写しましょう
葉の向こう側は見えないので
省略します。

葉の全体を薄緑色(1005)で
着色します。

このように葉の下地が描写されました。
9 着色(葉‐②)

上側の葉2枚を深緑色(911)で
陰影を着色します。
(葉の多くは内側に反っています)

このように上の2枚が表現できました。
10 着色(葉‐③)
下側2枚の葉は陰側のため、さらに
濃い目に深緑色(911)を着色します。

花弁の影を着色します。

日差しの当たる範囲を塗り残しながら
着色していきますが、光沢の範囲は
皆さんの感覚で描写してかまいません。

陰側(右側)はマットに(ベタ塗り)
着色していきます。

このように葉が表現されました。
(もう少し濃い目に描写してもかまいません)
11 着色(枝)

枝の下地を黄土色(941)で着色。

枝の陰影をこげ茶色(945)で描写します。

以上で華やかな椿の完成です!

いかがでしたでしょうか、
冬に色鮮やかに咲く椿が
仕上がったでしょうか。
花びらの着色をメインに描写して
いきましたが、葉の描写もさらに細かく
表現することでリアルになっていく
と思います。
それではこれからも
新講座のご案内など不定期ですが
発信してまいりますので
どうぞお楽しみに!
アトリエたくみ
画家・たくみ









-300x200.jpg)

